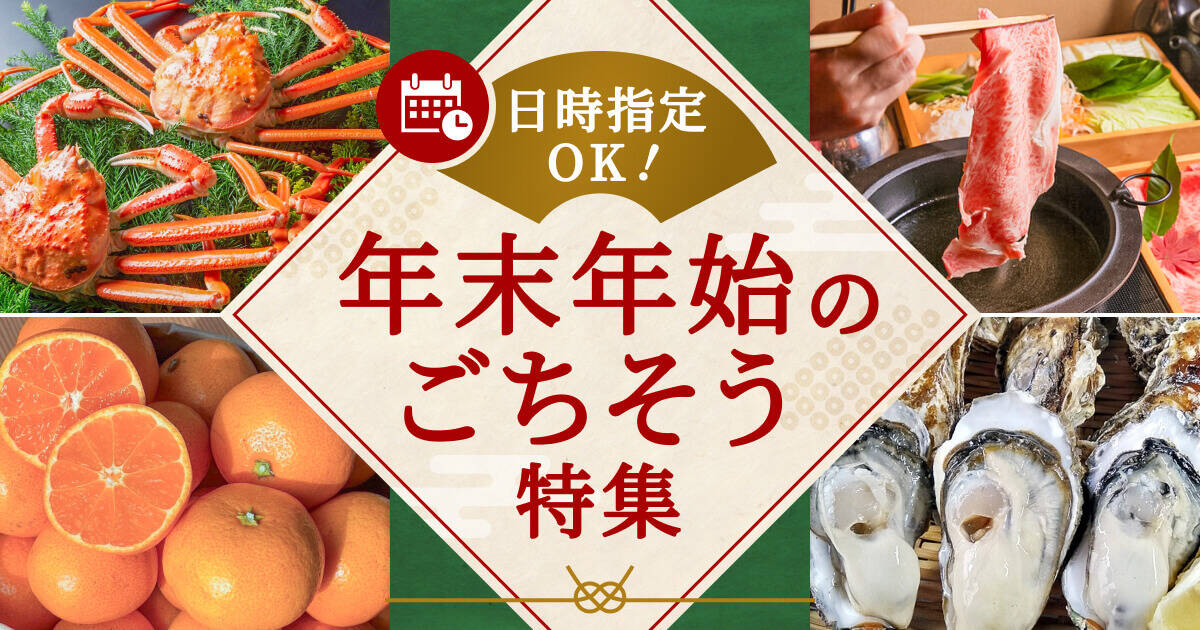【花言葉はどう決まる?】あなたの知らない「花」のヒミツをご紹介!
私たちの生活に潤いと癒しをもたらしてくれる、花。日本では時期によって鮮やかな美しい花々が咲き誇り、その魅力は国内外で高く評価されています。
日本最大の特徴でもある「四季」とは切っても切り離せず、その美しさを彩ってきたのは花の存在と言っても過言ではないでしょう。
食べチョクはもちろん、日々の生活の中でも、花屋さんやスーパーの一角、よくよく見れば公園や川辺など、身近なところにある花ですが、実はその一輪一輪に深い魅力が秘められていることをご存知でしょうか。
今回は、そんな花の歴史や特徴、さらには花言葉の決まり方まで、普段なかなか着目しない"花のヒミツ"をご紹介します。
日本人が花を愛してきた歴史
日本における花を愛でる文化は、古代から現代に至るまで、時代とともに発展し、多様な形で人々の生活に根付いてきました。その歴史を振り返ると、花と人々の深い関わりが見えてきます。
古代~奈良時代:仏教伝来と花の供養

日本における花文化の起源は、仏教の伝来とともに始まったとされています。仏前に供える「三具足」(華瓶・燭台・香炉)の一つである「華瓶」に花を飾る習慣が、その礎です。 また、奈良時代にはウメの栽培が始まり、花を愛でる文化が芽生え始めました。
平安時代:サクラの台頭と花見の始まり

平安時代になると、花見の対象がウメからサクラへと移行しました。記録に残る日本初の花見は、812年に嵯峨天皇が神泉苑で催した「花宴の節」であり、この頃からサクラを愛でる文化が広がり始めたのだとか。また、『古今和歌集』にはサクラを題材とした和歌が多く収められており、サクラが春の花の象徴として定着していったことが伺えます。
室町時代:生け花の成立

室町時代には、生け花が成立し、花を室内で鑑賞する文化が発展しました。生け花の歴史は長く、飛鳥時代にその原型となる文化が存在していたと言われていますが、室町時代に入ると社会の変化に応じた形式が創出され、多くの人々に受け入れられていきました。
江戸時代:庶民にも愛される存在へ

江戸時代には、園芸文化が庶民の間にも広がり、多くの花卉品種が改良されました。特に、ハナショウブやアサガオなどの品種改良が進み、花の鑑賞が庶民の娯楽として定着しました。また、花を売り歩く「白川女」の存在など、花が人々の生活に深く根付いていたことが伺えます。
現代:多様な花文化の共存

現代の日本では、伝統的な生け花や茶花の文化に加え、フラワーアレンジメントやガーデニングなど、多様な花文化が共存しています。また、サクラの花見は今もなお春の風物詩として全国各地で親しまれています。
これらの文化は、古代から続く花を愛でる心が形を変えながら受け継がれてきた証と言えるでしょう。
四季折々、日本を彩る花

日本は四季がはっきりしており、その季節ごとに多彩な花が栽培されています。春には桜やチューリップ、夏にはひまわりや朝顔、秋にはコスモスや菊、冬にはシクラメンやポインセチアなどが代表的です。これらの花々は、観賞用だけでなく、贈答用やイベント装飾など、さまざまな場面で活用されています。
花言葉はどう決まる?
ギフトで花束を贈る時、自分のために花を選ぶ時など、花を購入する時は必ず意識してしまう「花言葉」。各種の花に象徴的なメッセージが込められています。
これらはどういった形で決まるのかご存知でしょうか。
そもそも花言葉の起源は、18世紀のヨーロッパで広まったものとされています(諸説あり)。特に、フランスやイギリスで「花の言語(Language of Flowers)」として、花を使ったコミュニケーションが流行し、これにより、花に特定の意味を持たせる文化が定着していったそうです。

花言葉の決定には複数の要素が影響します。
(1)花の特徴や性質
花の色、形、香り、咲く季節など、その花自体の特徴は花言葉によく反映されます。例えば、ヒマワリは太陽に向かって咲く性質から「憧れ」や「敬慕」といった花言葉が付けられています。

(2)神話や伝説
特定の花にまつわる神話や伝説が、その花の花言葉の由来となることも多々あります。例えば、ギリシャ神話に登場するアネモネは、悲恋の物語から「はかない恋」という花言葉が付けられています。

(3)歴史的背景や文化
花が持つ歴史的な背景や、その花が使用されてきた文化的な文脈も、花言葉の決定に影響を与えます。例えば、ユリはキリスト教において純潔の象徴とされており、「純潔」という花言葉が付けられています。

なお、花言葉を決定するための正式団体等が存在するわけではなく、その時代に普及したメッセージがそのまま定着することが多いようです。
食卓を彩る「食べられる」花!?

エディブルフラワー(食用花)は、料理やスイーツの彩りとして近年注目を集めています。ビオラやバラ、パンジー、ナデシコ、ナスタチウム、マリーゴールドなどが代表的な品種で、それぞれに独特の風味があります。
これらの花は、サラダやデザートのトッピングとして使用され、料理を華やかに彩ります。ただし、食用として栽培された花を使用することが重要で、観賞用の花は食用に適さない場合があるため注意が必要です。
生産者さん直伝!花を100倍楽しむコツ
10,000軒以上の生産者さんが登録する食べチョクならでは!花卉の生産者さんに、届いたお花を100倍楽しむ方法を教えてもらいました。
いい状態の花を見分けるには?

- 茎が硬く花びらが傷んでいないものを選んでください。新鮮なものはふんわりと優しい香りがします。(花園芸の豊田さん)
- 花農家で使用した親株などはお得です。親株は複数の株から選別した優秀な株ですので、生育もよく花数も良いことが予想できます。ある一定の確率で変異した株が出現します。葉に斑が入ったり、花が八重咲になったりします。(みんなの花屋さん ほのかさん)
花を美しく長持ちさせる方法は?

- 届いたらすぐに深水で水揚げをする、暑いところには置かない。水切りをする、花持ち剤を入れる、などが大切です。(安間ばら園さん)
- 花を生ける水に食器用洗剤一滴、バクテリアの繁殖を抑えます。(SEVEN BOWLsさん)
- 鉢花も切花と同じで温度が低い方が長持ちします。なので冬の方が長く楽しめます。日当たりが良く温度低めが最適です。(須藤園芸さん)
あまり知られていない、マニアックな楽しみ方は?

毎日を彩る、奥深い「花」の世界へようこそ!

忙しなく過ぎる、大変なことも多い日々。でもその日常に「花」があると、どこか心安らぎ、毎日が鮮やかに彩られるように感じます。
あなたの心の癒しに、大切なあの人への贈り物に。日本人が古より愛してきた花の色どりを添えてみませんか。