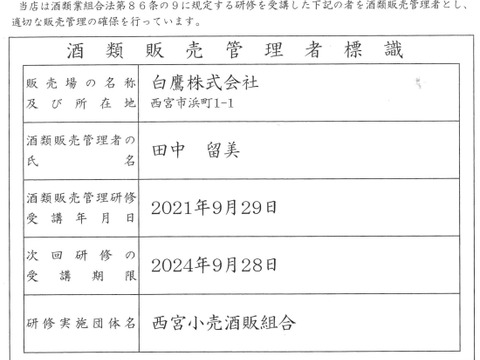<味>
米の旨味を最大限に活かした、キレと力強い飲み口。灘の生一本の名にふさわしい特別純米酒。
<こだわり>
生もと造りで醸しております。
<産地の特徴>
兵庫県三木市吉川町の契約農家から仕入れる特A地区産山田錦を100%使用しております。
<詳細>
アルコール度数 16.0~16.9
日本酒度 +3
精米歩合 70%
<おススメの飲み方>
常温、ぬる燗、燗がおすすめです。
※画像はイメージです
商品説明をもっと見る
米の旨味を最大限に活かした、キレと力強い飲み口。灘の生一本の名にふさわしい特別純米酒。
<こだわり>
生もと造りで醸しております。
<産地の特徴>
兵庫県三木市吉川町の契約農家から仕入れる特A地区産山田錦を100%使用しております。
<詳細>
アルコール度数 16.0~16.9
日本酒度 +3
精米歩合 70%
<おススメの飲み方>
常温、ぬる燗、燗がおすすめです。
※画像はイメージです
商品説明をもっと見る
注意事項
20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。
20歳未満の方にはお酒を販売いたしません。
便利なお届け通知や、限定おすすめ情報も!
いつでも、どこでも、農家・漁師と繋がろう!